
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、遺産分割手続きや、相続争いの相談や依頼ができます。
相続争いや遺産分割手続きにお悩みの方は、以下の記事を参考にしてください。
突然の肉親の死亡に悲しむ間もなく、役所への届出やお葬式の準備、法事などに追われてようやく一息ついたら、相続税の申告や相続人同士の遺産分割の話し合いが始まります。兄弟間のことなので譲り合えば円満に遺産分けができると思っていると、予想外に揉めて困ることがあります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって最適な相続争いの解決方法を考え、解決のためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
相続(遺産分割、遺言、相続手続き)について詳しく知りたい方は、『よくある質問(相続編)』をご覧ください。
(1)ひと目で分かる『相続手続き』
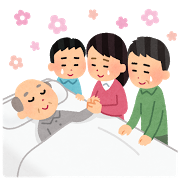
身内が亡くなると、残された家族はさまざまな相続手続きをしなければなりません。相続の開始から、相続税の申告・納付まで相続手続きのスケジュールを確認しておきましょう。『相続手続きチェックシート』(PDF)
(1)7日以内
① 死亡届の提出(市役所)
死亡届の用紙は、市役所や病院におかれています。作成後、市役所に提出します。死亡届を提出すると火葬や墓地への埋葬の許可(死体埋火葬許可証)がもらえます。
「死亡診断書」のコピーをとっておくと、各種手続きの際に助かります。
② 各種名義変更(各社・各機関)
・借家→大家さん・管理会社に契約者変更手続きを依頼。
・電気・ガス・水道→各社で更新又は解約手続き。インターネットで手続きできる所も。
・電話・インターネット→各社で手続き。気づかず口座引落しされやすいので注意。
・運転免許証→警察署などの窓口で返納手続きをする。
(2)14日以内
① 世帯主変更届(市役所)
市役所によっては、自動的に変更してくれるところもあります。
② 国民健康保険証・介護保険被保険証の返還・脱退手続き(市役所等)
国民健康保険等の被保険者が死亡した場合には、保険証の返還などの手続きをします。
会社の健康保険の場合、5日以内に保険証返納が必要なのでご注意ください。
葬祭費や埋葬料の支給も受けられますので、2年以内に支給申請もお忘れ無く。
③ 未支給の年金などの請求(年金事務所か年金相談センターに問合せ)
被相続人が国民年金などの被保険者の場合、「年金受給権者死亡届」を提出します。
条件を満たしている場合には、遺族基礎年金などを請求できます。
厚生年金等の場合、10日以内に手続きが必要なのでご注意ください。
(3)3か月以内
① 相続放棄・限定承認の申立て期限(家庭裁判所)
遺産相続では、プラスの財産よりも債務の方が多いこともあります。このような場合、被相続人の死亡を知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないとき、3か月以内であれば、限定承認をすることもできます。
いずれの手続きも、家庭裁判所に申立てが必要です。弁護士に依頼することも可能です。
② 相続人の確定(市役所等)
相続放棄をするかどうかは、相続人と遺産を確定しなければ決められません。
誰が相続人かを確定するには、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍と各相続人の戸籍が最低限必要です。各人の本籍地で戸籍を取得します。
ご自身で戸籍をとれない方は、弁護士に依頼することもできます。
③ 遺産の確定
相続放棄をするかどうかを決めるには、被相続人の残した財産をしっかり調査し、整理することが必要です。弁護士に調査を依頼することも可能です。ただし、遺産の一部が発見できないこともあります。
(4)4か月以内
① 所得税の準確定申告をする(税務署)
生前の被相続人が自営業者などで、毎年確定申告をしていたような場合には、準確定申告の手続きを行わなければなりません。
準確定申告は、準確定申告書を相続人全員が連署して、所轄の税務署に提出します。
『相続円満サポートエイト』の税理士に依頼できます。(クリックして下さい)
(5)10か月以内
① 相続税の申告・納付(税務署)
相続税の申告と納付が必要な場合、被相続人死亡の翌日から10か月以内に、税務署へ申告書を提出し、相続税を銀行振込みしなければなりません。
相続人全員で1通の申告書に署名・捺印をすることが難しい場合には、相続人それぞれが作成して提出することもできます。
『相続円満サポートエイト』の税理士に依頼することもできます(クリックして下さい)
② 遺産分割協議・遺産分割調停(弁護士等)
相続税の申告が必要な場合、申告期限までに、相続人全員で遺産の分け方を決めて、遺産分割合意書等を作成する必要があります。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。弁護士に依頼することも可能です。
遺産分割調停中は、法定相続分で相続税の申告・納付をし、調停後に更正の請求をすることができます。ただし、相続税に関する特例が利用できないので要注意です。
(6)1年以内
① 遺留分減殺請求権の行使(弁護士等)
遺言で一部の相続人が何ももらえない内容になっていることもあります。
その場合でも、相続人には最低限の遺産をもらえる権利(遺留分)があります。
遺留分は、被相続人死亡日及び、遺留分侵害があると知ったときから1年以内に行使しない場合、権利主張できなくなります。1年以内に権利行使したことを証明するために、遺留分減殺請求は、内容証明郵便(配達記録付)で行いましょう。
遺留分減殺請求及びその後の交渉を弁護士に依頼することも可能です。
(7)2年以内
① 高額診療費の支給申請(市町村、協会けんぽ等)
被相続人が死亡直前の病気やケガで高額の医療費を払った場合、請求すれば、自己負担限度額を超えた分を払い戻してもらえます。
診療月の翌月から2年以内に行います。
(8)3年以内
① 生命保険等の保険金請求(各保険会社)
被相続人が、生命保険に加入していた場合は、死亡保険金の請求手続きを各保険会社に行います。
死亡保険金には、相続税、所得税、贈与税のいずれかがかかります。どれに該当するかは、保険契約内容によって異なります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、1人1人異なる相続トラブルに対して、相談者の立場にたって最適な解決を考え、解決のためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
相続税の申告、遺産の評価(不動産、株式等)、相続税対策(生前贈与等)、遺言作成、相続登記などの相続全般に関する相談は、「相続円満サポートエイト」が、<税理士・弁護士・司法書士・社労士・不動産鑑定士>の各専門家で連携して最後まで皆様をサポートいたします。
ご相談予約のお電話は、076-249-8553までお願いします。
(2)相続人を調べる (戸籍で確認する)

相続の手続きを進めるには、誰が相続人か把握する必要があります。
特に、故人に子がなく故人の兄弟が相続する場合や、再婚や認知などで腹違いの息子や娘がいる場合には、誰が相続人かしっかり調べないといけません。
① 法定相続人と法定相続分は民法で決まっています。
| 子ども (二人以上いる場合は、合計) |
配偶者 | 父母 (死亡時は祖父母) |
兄弟姉妹 (二人以上いる場合、合計) | |
|---|---|---|---|---|
| 子どものみ (孫以降、代襲) |
全部 | --- | --- | --- |
| 子どもと配偶者 | 2分の1 | 2分の1 | --- | --- |
| 配偶者と父母 | --- | 3分の2 | 3分の1 | --- |
| 父母のみ (死亡時は祖父母) |
--- | --- | 全部 | --- |
| 配偶者と兄弟姉妹 | --- | 4分の3 | --- | 4分の1 |
| 兄弟姉妹のみ (甥姪代襲相続) |
--- | --- | --- | 全部 |
相続人の範囲(法定相続人)と遺産の取り分(法定相続分)は民法で決まっています。
相続人全員の話し合いで、法定相続分と異なる割合で相続することも決められます。
故人の死亡時点で、相続人(子や兄弟)が死亡していた場合、孫や甥姪が相続人となることがあります(代襲相続)。
遺産分割をする際、一部の相続人を排除したり、相続人と気づかずに協議に呼ばなかったりした場合、その遺産分割は無効となり、やり直しになりますので、ご注意ください。
② 相続人を調べるために必要な戸籍
戸籍は、本籍地の市町村役場において、窓口か郵送で取得します。
通常、次の順番で戸籍をとっていきます。
(1)故人(被相続人)の生まれてから死ぬまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)全部
被相続人がずっと本籍を動かしいなければ、一つの役場で全部集まります。
本籍を動かしていれば、動かす前の役場で古い戸籍をとる必要があります。
(2)子(又は孫)の戸籍(除籍、改製原戸籍)全員分
子が結婚したりすると、親(被相続人)の戸籍から出ています。
その場合、子(子が死亡の場合は孫)の戸籍をとる必要があります。
(3)祖父母の戸籍(除籍、改製原戸籍)全員分
子がいない場合、祖父母・曾祖父母が相続人になります。
祖父母・曾祖父母の死亡時、兄弟が相続人となります。
祖父母らの生死に関わらず、祖父母らの出生時から死亡までの戸籍が必要です。
(4)兄弟姉妹(又は甥姪)の戸籍(除籍、改製原戸籍)全員分
子がいない、祖父母ら死亡の場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡の場合、その甥姪が相続人になります。
そのため、兄弟姉妹の戸籍、甥姪の戸籍が必要になります。
先代、先々代の相続をほったらかしにしていると、更に戸籍をとる必要がでてきます。
特に、遺産に不動産(土地・建物)がある方は、相続手続きをほったらかしにしてはいけません。
③ 相続人の調査を弁護士に依頼できます。
相続人を調べるための戸籍を集めるのも、かなり大変です。
戸籍集めにくじけた方は、弁護士に依頼することもできます。
弁護士や法律事務所によって、料金・費用は異なりますが、白山・野々市法律事務所では、以下の料金・費用で戸籍をお取り寄せして、相続人をお調べいたします。
| 戸籍等の取得 | 手数料 | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ①10通まで | ①5万円(税込55,000円) | ・郵送料 ・為替手数料 ・発行手数料 (市町村) など |
相続関係図 作成料込 |
| ②11通目以降 | ①(10通目までの5万円(55,000円) +1通ごとに2,000円(2,200円) |
同上 | 同上 |
白山・野々市法律事務所に頼めば、相続人が多くない場合、5万円(税込55,000円)+実費で弁護士に戸籍を集めてもらい、相続人を調べてもらうことができます。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
(3)相続財産を調べる

財産を分けたり、相続税を申告したり、相続放棄をするかどうかを決めるためには、故人の財産をしっかり調査し、整理する必要があります。
① 遺産を調べる方法
遺産の調査は、故人(被相続人)の身の回りから始めるといいでしょう。
遺産には現金や車などの家財など見て分かるものだけではなく、通帳や保険証書、不動産の権利証のように保管されている書類で確認できるものもあります。
株の取引報告書、納税通知書のように定期的に送られてくる郵便物からも判断できます。
故人が貸金庫を借りている場合には、貴重品が保管されていることもあります。
貸金庫を借りているかどうかは、使用請求書や通帳から手数料が引かれていることなどで分かります。
また、インターネット銀行での取引や株、投資信託など書類が発行されないものもあります。故人(被相続人)のパソコンメールなどに、取引報告や残高通知などが来ている場合もありますので、メールやデータを一度確認してください。
※ 借金等について
借金等の債務も遺産です。故人(被相続人)の身の回りに借用書や返済書類などがないか確認してみてください。また、請求ハガキなど郵便物を見て発見できることもあります。
② 遺産の価値を調べる
遺産の価値は遺産の種類によって調べ方が異なります。典型的なものを例示します。
自分で調査できますが、不動産や株式などの評価が難しいものは税理士さんに相談しましょう。
| 価値の算定方法 | 調べ方 | 調査の難易度 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | 死亡日に故人の手持ちのお金 | 故人の身の回りを確認する。 | 容易 |
| 預貯金 | 死亡日の残高 | 口座のある金融機関窓口 残高証明書を発行してもらう |
容易 |
| 公社債 | 公社債の種類ごとに定められた評価方法 | 取扱い金融機関の窓口 残高証明書を発行してもらう。 |
容易 |
| 投資信託 | 死亡日の価格 | 取扱い金融機関の窓口 価格証明書を発行してもらう。 |
容易 |
| 株式 | 上場株は、死亡日の終値(他の評価方法あり) 非上場株は、定められた評価方法に従う |
上場株は新聞の株式欄。 非上場株は、税理士さん等に評価額を計算してもらう。 |
非上場株の場合、難 |
| 土地 | 路線価方式、倍率方式など評価方法がある。 借地、貸地は算定式が別にあり。 |
路線価など公開情報を元に算定できなくはないが、難しい。 税理士さん等に計算してもらった方が良い。 |
難しい |
| 建物 | 固定資産評価額。 貸し家は算定式が別。 |
固定資産評価額は、市役所で証明書をもらえば分かる。 | 普通 |
| 自動車 | 同種の市場価格 | 車屋で査定してもらうなど | 普通 |
| 貴金属 | 同種の市場価格又は鑑定額 | 買取屋に査定してもらうなど | 普通 |
相続税の申告、遺産の評価(不動産、株式等)、相続税対策(生前贈与等)、遺言作成、相続登記などの相続全般に関する相談は、「相続円満サポートエイト」が、<税理士・弁護士・司法書士・社労士・不動産鑑定士>の各専門家で連携して最後まで皆様をサポートいたします。ご相談予約のお電話は、076-249-8553までお願いします。
③ 弁護士に依頼できます。
預貯金・投資信託の調査や不動産の有無等の調査を弁護士に依頼することができます。
| 手数料 | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 預貯金の調査 | 2万円 (税込2万2000円 |
郵送料 発行手数料(金融機関等) |
別途、戸籍取り寄せ費用(10通まで5万円(税込55,000円)がかかる場合があります。 口座のある金融機関が分かっている場合に限ります。 |
| 投資信託・公共債の調査 | (1つの取扱い金融機関ごと)1万円(税込1万1000円) |
同上 | 同上 |
| 不動産の調査 | 1万円(1万1000円) | 同上 | 同上。 登記情報を取得しますが、評価額は算定しません。 |
非上場株式の評価や土地・建物の評価などは、税理士や不動産鑑定士にご相談ください。
上記料金表とは異なりますが、遺産の評価(不動産、株式等)に関するご相談・ご依頼は、「相続円満サポートエイト」が、<税理士・弁護士・司法書士・社労士・不動産鑑定士>の各専門家で連携して最後まで皆様をサポートいたします。
ご相談予約のお電話は、076-249-8553までお願いします。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
(4)相続放棄の申立て

相続する財産に多くのマイナスの財産が含まれていた場合、その負債を相続しなくてすむように相続放棄をすることができます。
相続放棄とは
相続は、故人のプラスの遺産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことになります。借金だけ引き継ぎませんということはできません。
借金が多い場合、「遺産は一切いりません」と相続放棄することができます。
相続放棄をしても、故人の生命保険の受取人であれば保険金を受け取れますし、死亡退職金も受給権があればもらえます。
相続放棄の期限(死亡後3か月以内)
相続放棄の期限は、被相続人(故人)が死亡したのを知った日から3か月です。
被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄は、相続人がそれぞれ手続きをしなければいけません。
相続放棄に必要な書類
①相続放棄申述書
②申立人(相続人)の戸籍
③被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)
④被相続人の住民票除票または戸籍付票
⑤(父母や兄弟が相続人の場合)父母や祖父母の戸籍(除籍・改製原戸籍)
弁護士に依頼できます。
申立書の書き方が分からない、戸籍等を集められない、やむを得ず期限の3か月を超えて相続放棄をしたいという方は、弁護士に依頼することができます。
弁護士に依頼した場合の料金・費用は、以下のとおりです。
| 手数料(税別) | 実費 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 申立人1名ごとに 5万円(税込5万5000円) |
郵送料 裁判所費用 など |
別途、戸籍取り寄せ費用 (10通まで5万円(税別) がかかります。) |
例えば、被相続人の兄弟2名が相続人であり、2名で相続放棄する場合、10万円(税別)+実費(戸籍持参の場合)で弁護士に相続放棄を依頼できます。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
(5)遺産分割

遺産分割手続き
遺産分割には、遺言・協議・調停・審判の4種類の手続きがあります。
①遺言による指定分割
被相続人が遺言に定めた方法で分割を行うことです。
相続では、「遺言による相続は法定相続に優先する」という大原則があり、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容のとおり遺産分割されます。
遺言書のとおり遺産を分配するために、「遺言執行者」を遺言書で決めておくこともできます。白山・野々市法律事務所の弁護士に「遺言執行者」を依頼した場合の料金は、次のとおりです。
| 手数料 | 実費 | |
|---|---|---|
| 遺言執行者報酬 | 遺産額の2.5%(税込2.75%) ※最低額35万円(38万5000円) |
遺産の分配にかかった支出 (郵送料、口座解約手数料等) |
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
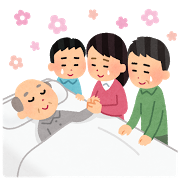
②協議分割(遺産分割協議)
相続人全員の合意によって遺産分割を行うことです。
相続人全員の合意があれば、法定相続分と違う割合での遺産の分配をすることもできます。
遺産分割協議を弁護士に依頼することもできます。白山・野々市法律事務所の弁護士に依頼する場合の料金は、次のとおりです。
| 着手金 |
報酬金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺産分割交渉 | 20万円 (22万円) |
~300万円は17%(18.7%) ~3000万円は11%(12.1%)+20万円(22万円) ~3億円は7%(7.7%)+150万円(165万円) |
※着手金・報酬金の他に、 実費(郵送料、発行手数料 など)がかかります。 ※別途、調査や資料収集に費用がかかります |
※他に、実費がかかります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

③調停分割(遺産分割調停)
家庭裁判所の調停によって遺産分割を行うことです。
調停では調停委員が相続人から個別に話を聞き、遺産分割方法を調整してくれます。
特別受益や寄与分についての調整も試みてくれます。
相続人の1人でも遺産分割案を拒否した場合、何も決まらないまま調停は終わり、審判に移行します。
遺産分割調停を弁護士に依頼することもできます。白山・野々市法律事務所の弁護士に依頼する場合の料金は、次のとおりです。
| 着手金 (税別) |
報酬金(税別)) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺産分割調停 |
40万円 (税込44万円) |
~300万円は17%(18.7%) ~3000万円は11%(12.1%)+20万円(22万円) ~3億円は7%(7.7%)+150万円(165万円) |
※着手金・報酬金の他に、 実費(郵送料、発行手数料など) がかかります。 ※別途、調査や資料収集に 費用がかかります |
※ 他に実費がかかります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。

④審判分割
家庭裁判所の裁判官が分割方法を決める手続きです。
調停と異なり、相続人の一部がごねても、裁判官が分割方法を決めてくれます。
裁判官の決めた分割方法に不服がある方は、高等裁判所に抗告することもできます。
遺産分割審判や抗告を弁護士に依頼することもできます。白山・野々市法律事務所の弁護士に依頼する場合の料金は、次のとおりです。
| 着手金 (税別) |
報酬金(税別) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 遺産分割 審判 |
40万円 (税込44万円) |
~300万円は17%(18.7%) ~3000万円は11%(12.1%)+20万円(22万円) ~3億円は7%(7.7%)+150万円(165万円) |
※遺産分割調停 から依頼の場合 は着手金不要。 |
| 抗告審 | 40万円 (税込44万円) |
抗告が認容されて増額分 20%(税込22万円) 増額がない場合は0円 ※遺産分割審判から依頼の場合は同審判の報酬金が必要となる。 |
※遺産分割審判 から依頼の場合 は着手金不要。 |
※ 他に実費がかかります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
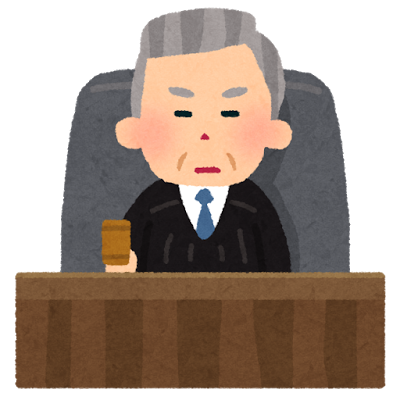
(6)遺留分

遺言によっては、一部の相続人に遺産がもらえない内容になっていることもあります。そのような場合でも、相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の取り分(遺留分)が認められています。但し、1年以内に請求をする必要があります。
1 遺留分
民法は、遺言の内容にかかわらず、相続財産のうち一定割合は最低限の取り分(遺留分)として、相続人がもらえるようにしています。
2 遺留分を主張できる人(兄弟姉妹以外の相続人)
遺留分(最低限の取り分)を主張できるのは、相続人です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分を主張できません。
つまり、被相続人に妻子がおらず、父母も死んでいる場合、遺言で兄弟姉妹以外の人に全財産を遺贈しても、兄弟姉妹は文句が言えないということになります。
遺留分権利者は、原則、遺産の2分の1(父母が相続人の場合は3分の1)を自己の法定相続分に応じて、遺留分侵害者に請求することになります。
3 遺留分の主張方法と期限
遺留分は、遺留分侵害者(全部相続した人、受贈者や受遺者)に対し、「遺留分減殺請求」をすることで行使できます。
被相続人の死亡日及び遺留分侵害があると知った日から1年以内(死亡日から10年以内)です。
期限内の請求であることを後日証明する必要がでてきますので、内容証明郵便(配達証明付)で請求することが多いです。
4 遺留分侵害額請求後の手続き
遺留分侵害額請求をした後、遺留分侵害者に弁償の話し合いをしていきます。
遺留分侵害者は、金銭弁償をして侵害分を返すことになります。
話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の調停で解決を図ることができます。
調停不成立の場合、家事審判ではなく、地裁に民事訴訟を提起する必要があります。
遺産分割調停を弁護士に依頼することもできます。白山・野々市法律事務所の弁護士に依頼する場合の料金は、次のとおりです。

| 遺留分 | 着手金 手数料 |
報酬金 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 遺留分 減殺通知書 |
1万円 (税込1万1000円) |
なし | 必要に応じて、 戸籍取得費用や 遺産調査費用が かかります。 実費(郵送料等) がかかります。 |
| 遺留分侵害額請求 交渉 |
20万円 (税込22万円) |
~300万円は17%(18.7%) ~3000万円は11%(12.1%)+20万円(22万円) ~3億円は7%(7.7%)+150万円(165万円) |
同上 |
| 遺留分侵害額請求 裁判 |
40万円 (税込44万円 |
同上 | 同上 |
※ 他に実費がかかります。
初回法律相談無料の白山・野々市法律事務所では、豊富な経験に基づき、相談者の立場にたって相続争い(遺産分割、遺留分、特別受益、遺言等)を解決するためのお手伝いをいたします。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。
(7)相続全般について相談できるところ
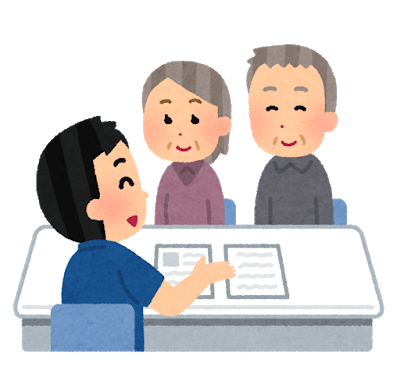
相続円満サポートエイト
相続について、8名の専門家(弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士ら)が連携して、相続手続き全般、相続税申告や相続トラブルの解決のトータルサポートをしています。
相続手続きといえば、どの専門家に依頼しますか?
弁護士でしょうか?税理士でしょうか?
相続税の申告では、「税理士」、相続の登記では、「司法書士」、相続の争いになれば、「弁護士」の出番となります。
相続手続きでは、「場面ごとに、専門家を探さないといけないの!?」と嘆かれる方は、実際とても多いのです。
そこで、相続手続き全てをお助けするために、野々市の税理士・弁護士・司法書士など8名が集まって、「相続円満サポート8」を結成しました。
毎月8がつく日(8日、18日、28日)に、無料相談を開催しています。
076-249-8553(専用ダイヤル)
までお気軽にお電話ください。
白山・野々市法律事務所では、安心して相談に来ていただけるように、初回の法律相談を無料でできるようにしています。
もちろん、相続(遺産分割、遺言、寄与分、特別受益など)の相談も無料です。
また、「弁護士費用(料金)」についても、HP上で明記しています。
安心してご依頼ください。
ご予約は、電話(076-259-5930)からお取りください。